破滅型中華料理店
2012/12/01 Sat 00:16
その路地を通る度に、いつか必ず入ってみたいと思う中華料理店が新宿にあった。
そこは、もう素晴らしく昭和。
アンダーワールドな香りがプンプンと漂っていた。
店の前に赤錆だらけの出前箱(岡持ち)が無造作に転がり、屋根のシートに書かれた店名はほとんど擦り切れ、そして真冬でも『冷やし中華はじめました』の涼しげなちらしが貼ってある。
僕はいつもその店の前を通る度に、埃だらけの引き戸サッシから店内をソッと覗いては、
絶対に泉谷しげるがいるはずだ
と、想像しては背筋をブルっと震わせていたのだが、しかし、いつも店は閉まっており、その店に潜入するチャンスは一度もなかった。

(シャブ中を演じる若い頃の泉谷しげる。※川俣軍司ではありません)
ちなみに、僕は『危険な店』や『ムカつく店』といった、いわゆる『ダメ店』が大好きな変態だ。
これらの店の店主やそこに集まる客というのは大概が破滅型人間であり、そんな彼らを最高の文学だと思って止まない僕は、そこでじっくりとその破滅型人間の行動を観察するのが好きなのだ。
そんなある日、遂にその店に潜入するチャンスが訪れた。
それは、歌舞伎町の風林会館で仕事の打ち合わせをした帰り道、時刻は深夜2時だった(こんな場所でこんな時間まで打ち合わせをする事自体が既に変態)。
細い路地を西新宿に向かって歩いていると、いつも電気が消えている中華料理店にポッカリと灯が灯っていた。
あ!やってる!と、子供のように一瞬目を輝かせた僕は、問答無用で足を速め店の前へ。
店前では、油で真っ黒に汚れた換気扇がゴーーーーッと不気味な音を立て、そこから焦げた油の匂いがムンムンと漂っていた。
店内からは、中華鍋が奏でる「カン、コン」という音が響き、やたらとうるさいテレビの音が聞こえる。
絶対に泉谷しげるがいるはずだ
僕はそう確信しながらも、その油でネトネトになった引き戸サッシを、恐る恐る開けたのだった。
僕を出迎えてくれたのは、やっぱりねと言うか、ホラねと言うか、凄まじく薄汚れたサッポロビールの水着ポスターだった。

(イメージ)
そのビキニ女が誰なのかはわからないが、しかしその髪型やデザインからして、恐らくそのポスターは80年代の物と思われる(こんなどーでもいいモノを、店の入口に30年近く飾っているとは!)。
僕は、その時代錯誤なハイレグ美女に感動というか恐怖を感じながら、とりあえず目の前のカウンターに座ったのだった。
さりげなく店内を見回した。
天井は茶色かった。きっと最初は白だったのだろうが、今は蓄積された中華の油と煙草のヤニで見事に茶色かった。
天井の隅で蜘蛛の巣まみれになっている浅草酉の市の熊手。その横で天釣りされている茶色い「招き猫」。そしてその下の壁には「協栄ボクシングジム所属・元WBA 世界ライトフライ級チャンピオン」と肩書きが書かれた渡嘉敷 勝男のサインが淋しそうに貼られていた。
店内には、カウンターの中で中華鍋を振っている店主と、カウンターの真ん中でテレビを見ているサラリーマンと、そして奥のテーブルに労務者風の男がチビリチビリとビールを飲んでいた。
いるぞいるぞ破滅型人間共が……
嬉しくなった僕は、ワクワクしながらカウンターに散乱している油まみれの週刊誌をどけ、その奥で更に油まみれになっているメニューを見た。
ところで、コレ系の店というのは、基本的に『いらっしゃいませ』という歓迎の言葉は望めない。
しかも、お冷や(水)も出て来ないし、やたらとテレビの音ばかりがうるさい。
そんなお店に対し、大概の一般人はムカッと来るはずだ。
そして、ムカッと来た一般人は、家に帰るなりさっそくネットを開いては、Yahoo!のクチコミなんかに『この店、最悪!』などと書きまくり、挙げ句には自身のブログなんかで必死に悪態をつくのだろう(わざわざ写真付き)。
しかし、僕はプロだ。
コレ系のダメ店をわざわざ好む変態だ。
ハナっから『いらっしゃいませ』などという茶番な御言葉など期待していない。
だから全然腹は立たないのだ。
さっそく僕はメニューを見つめながら、奥にいる破滅型人間をソッと観察した。
カウンターの真ん中にいるサラリーマン。
虚ろな目でボンヤリとテレビを見つめ、時折、フッと小さな溜息をつきながら、思い出したかのように油でギトギトに輝く餃子を箸で突いている。
その雰囲気は、この世の全てが嫌になった人生漂流者のようであり、その横顔はまさしく太宰治そのものだった。
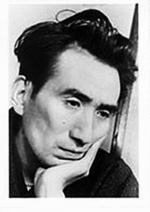
こんな妖気漂う破滅型人間を、僕は『虫の息タイプ』と呼んでいる。
ソッと彼の前に「はい」と青酸カリを出そうものなら、きっと彼は「すまないね」と一言呟き、迷う事無くその場で一気にグイッとやる事だろう。
一方、その奥のテーブルでグイグイとビールを飲んでいる労務者風のおっさん。
どことなく長門勇の匂いが漂って来る無骨者。

騒ぐわけでもなく、1人静かに黙って飲んでいるが、しかし、彼の背中には唯ならぬ粗暴さが漲っている。
こんな破滅型人間を、僕は『一触即発タイプ』と呼んでいる。
コレ系のタイプは非常に厄介だ。
いつも深酒しては最後にゃダラダラになっているタイプであり、決まって時代劇の酒処なんかでは、店の小娘なんかに「飲み過ぎですよ」なんて小言を言われている野武士だ。
彼には、いつ発狂するかわからないというスリルがあり、見ているだけでワクワクしてくる。
そんな脇役達をじっくりと観察すると、僕はいよいよ厨房で中華鍋を振る主役に視線を向けた。
ヤツはまだこちらを向いていない。
だから顔はわからないが、しかし、その病的に汚れた白衣から見て、かなりの破滅型だと僕は察した。
カン!コン!と、やたらとオタマで中華鍋を鳴らす。
それは、彼なりのパフォーマンスなのだろうが、しかしうるさくて堪らない。
僕は彼と御対面する前に、その中華鍋の中を見て、彼の中華料理人としての腕前を探ろうとした。
中華鍋の中でムニュムニュになっている野菜たち。
八宝菜なのか野菜炒めなのか、とにかくソレ系だ。
全然美味そうではないが、しかし、それなりにサマにはなっている。
中華鍋の振り方も、それなりにサマになっていた。
カン!コン!とやたらとうるさいが、しかし、まぁ、どこにでもいる中華料理人といった感じだ。
そんな店主が、手際よく皿の上にムニュムニュな一品を盛りつけた。
鶏ガラの香ばしい香りが狭い店内に濃厚にモワッと漂う。
店主は、皿に飛び散るネトネト汁もおかまいなしに、豪傑にもそれをダバダバと盛りつけると、その油ギトギトの手のままで皿を握った。
いよいよ、主役との御対面だ。
「はい、五目やきそば」
カウンターに振り向いた店主は仏頂面でそう言いながら、まるでそれを投げ捨てるかのように、太宰治の前にガコ!と乱暴に置いた。
五目やきそば?
一瞬僕はそのムニュムニュな一品に目を疑った。
が、しかし、そのムニュムニュな一品が五目やきそばというのも凄いが、客席に振り向いた店主の顔も凄かった。
その店主の顔は、まさしく、
不機嫌な石橋連司そのものなのだ!

瞬間、僕は嬉しさのあまり叫び出しそうになった。
この店内にこの客層、そして正体不明な五目やきそばと、不機嫌な石橋連司。
これは、西成の大衆食堂で萩原健一風の泥酔者と出会うくらい、山谷のホルモン焼き屋で『日本の将来」について討論を仕掛けて来る伴淳三郎風の酔っぱらいと出会うくらい、そのくらい貴重な出会いなのだ。
凄いぞ!凄いぞ石橋連司!
そう血肉を沸き踊らせていると、店主は不機嫌そうに僕を見つめながら「なんにする」と、ポツリと呟いた。
当然、敬語ではない。
その口調は、まさに〝面倒臭せぇなぁ感〟がムンムンと溢れており、ダメ店としてはホームラン級の口調だ。
僕はそこで初めて油ギトギトのメニューに目をやる。
店主はそんな僕に「フン」っと背中を向けると、奇妙な五目やきそばを作っていた中華鍋を、水の張ったシンクの中にジャワー!っと沈ませ、おもむろに薄汚れたエプロンの中からハイライトを取り出したのだった。
僕は、そんな連司を警戒しつつ、カウンターの上のメニューを隅から隅まで観察した。
そのメニューは、昔ながらの「置き型タイプ」で、もちろん中身は手書きだった。
ボールペンで殴り書きしている投げやりな所が妙に心地いい。
いつの物かもわからぬチャーハンの米粒がカピカピに乾涸びて付着している所など、問答無用で金賞受賞を差し上げたいくらいだ。
そんなメニューの中に、これまた凄いメニューを発見した。
五目チャーハン、中華飯、天津飯、とメシ物が続くその最後に、なんと、
『アジの干物』
という、実に場違いなメニューが紛れ込んでいるではないか!
僕は横目でソッと石橋連司を見つめた。
この御時世に堂々と客の前で銜え煙草を吹かしながら、中華鍋を面倒臭そうに洗っている。
もしかして、こいつは分裂病か?
そんな連司を見つめながら、僕はなぜ中華料理店で『アジの干物』なのかとアレコレ推理した。
もしかしたら、連司の実家は南伊豆なのかも知れない。
そこで八十を過ぎた老いたお袋がアジの干物をセッセと作っている。
それを連司は〝親孝行〟と題し、お袋のアジの干物を店で出しているのかも知れない……
いや、まてよ、もしかしたらこの男、浦安辺りの漁師なのかも知れない。
シケの時だけ東京にやって来てはこの店を開くという、いわゆるサイドビジネスでこの店を経営しているのかも知れない。
僕は全ての推理を「アホか」と打ち消すと、これはもう誰が何と言おうとやっぱりこれでしょ、とばかりに、
「とりあえず、アジの干物下さい」
と、言ってやった。
メニューの隅にひっそりと書かれたこの『アジの干物』に、なにか底知れぬ〝こだわり〟を感じた僕は、これを注文すれば、きっと連司は激しく心を打たれるだろうと狙って見たのだ。
出し抜けにそう言われた連司は、ハイライトを銜えたままジッと僕を見た。
その眉間にくっきりと浮かんだシワが「なぜ?」を物語っていた。
狙いは的中した、と思ったが、しかし、連司はおもいきり卓袱台返しをやらかした。
せっかく、絶対に誰も注文しないだろうと思われる『アジの干物』を注文してやったというのに、連司に感動はなさそうだった。
連司は気怠そうにハイライトをポリバケツの中に捨てると、無言のまま家庭用の冷蔵庫を開け、そこからガサゴソとパックを取り出した。
パックの中にはアジの干物が三枚眠っていた。
そんなパックの端には〖お得品!〗と書かれたステッカーが貼られており、それはどう見てもスーパーの特売品だった。
しかも、そのパックは大きさからして明らかに五枚入りであり、という事は、既に誰かが二枚を食っちまっているのだ。
連司は真っ黒なガス台の上にサビだらけの網を置き、そこにアジの干物をペタンっと敷いた。
中華用のせいかそのガス台の火はかなり強く、直火で焼かれる干物はみるみると焦げて行った。
しかし連司は平然としていた。
干物の焦げ臭ささもなんのその、厨房の中に置かれたドーナツ座席の椅子にドテッと座りながら、パラパラと週刊大衆を捲っている。
すると、さっそく奥のテーブルの野武士がその異臭に騒ぎ出した。
「おい、なんだか臭せぇな、おい」
さすが一触即発タイプだけあり、野武士のその語気は荒い。
確かに、中華料理屋で干物の匂いは不自然だが、しかし、そこが破滅型店のイイ所であり、その危険な情緒を存分に堪能できる所なのだ。
野武士は素早く反応してくれたが、しかし太宰はダメだった。
さすが虫の息タイプだけあり、これくらいの異臭では動じない。
そんな太宰は、相変わらず何かを思い詰めたように項垂れては、五目やきそばを箸で突きながら文学的な深い溜息をついている。
五目やきそばを見つめながら、きっと心の中で『生まれてすみません……』などと呟いているのだろう。
などと思っていると、いきなり太宰が連司に向かって呟いた。
「この五目やきそば、麺が入っていないようだが……」
太宰は悲壮感100%の表情でそう呟いた。
その顔は、「嗚呼、遂に私はやきそばにまで見捨てられたのか」と絶望しているような、そんな顔だった。
しかし連司は、そんな太宰の悲壮感を気にも止めてはいなかった。
「やっぱりそーだよな、俺もさ、鍋振りながら、なーんかおかしいなぁって思ってたんだよ」
連司はそうニヤニヤ笑うと、そのまま何事も無かったかのように、また週刊誌をパラパラと捲り始めたのだった。
太宰もそれ以上何も言わなかった。
虫の息タイプの破滅人間は、諦めるのが早い。
これが一触即発タイプの野武士だったらひと騒動起きる所が、しかし連司はさすがプロだけあって、ちゃんと客を見て商売しているようだ。
そうしている間に、僕のアジの干物は真っ黒焦げになった。
しかし連司は慌てない。
干物の端が黒炭になってカサカサと崩れ落ちているにも関わらず、連司はそれを菜箸で摘まみ上げると、龍のイラストが描かれたチャーハンの皿にパサッと置き、それを僕の前に「はい、干物」と面倒臭そうに置いたのだった。
とりあえず、箸で突いて見た。
半分以上は黒炭だったが、それなりに白い身もあった。
僕はそれを普通に食べた。
朝ご飯の時のように、ポソポソと骨を取りながら貧乏臭く食べた。
すると、いきなり僕の目の前に、ゴツッ!と音を立て何かが置かれた。
それは小さな碗に盛られた白米だった。
「えっ?」と僕が顔をあげると、連司はソッと僕から視線を反らしながら、更にチャーハンに付いて来る小スープを僕の前に置いた。
「サービスだよ……」
無表情の連司は寝起きのような声でそうポツリと呟くと、再びドーナツ椅子に腰を下ろしては雑誌をパラパラと捲り始めた。
「あぁ、どうも……」
そう呟いた僕は、複雑な気分で白米を見た。
やっぱり米は黄色かった。椀の端にはカリカリに乾いた米がくっ付いている。
スープも相当煮詰まっているようで、かなり塩っぱかった。
しかし、シャキシャキのネギと、仄かに香るゴマ油の香りが僕の食欲をそそった。
スープを全て飲み干した。椀の底に残るコショウまでも飲み干した。
椀の米粒もひとつ残らず平らげた。カリカリに乾いた米が奥歯にくっ付いて大変だったが全て平らげた。
が、しかし、さすがに半分以上焦げたアジはそれ以上食えず、焦げた部分だけこっそり残した。
気がつくと夜中の3時を過ぎていた。
この店は何時まで営業するのかとても気になったが、しかし、こんな破滅店でそれを聞くのは無粋すぎる。
破滅店というのは、やりたい時にやって、閉めたい時に閉めるのだ。
爪楊枝を一本抜き取ると、その先っぽにネズミ色の埃が付いて来た。
その爪楊枝で奥歯にくっ付いた忌々しいカリカリ米をガリガリと攻撃し、やっとの思いで撤去した。
すっきりした所で煙草に火を付けた。
今日日、堂々と煙草が吸える飲食店は皆無に等しく、こうして食後の一服ができるのも破滅店のいい所だ。
っていうか、煙草云々をいう前に、そもそもこの店は根本的に何かがおかしく、今更煙草があーだこーだという次元ではないのだ。
ぼんやりしながら煙草の煙を茶色い天井に燻らせていると、いよいよ奥の無骨者が動き出した。
「おい、俺の餃子はまだか」
そう唸りながらカウンターに振り向いた無骨者は、酒と日焼けと肝臓の悪さから凄まじい顔色をしていた。
すると連司は、無骨者に一言の詫びを告げる事も無く、
「ああ、忘れてた」
と呟きながら、油の飛んだ週刊大衆をパタンっと閉じると、
「食うのか?」
と面倒臭そうに聞いたのだった。
「あたりめぇだろ、俺ぁメシ食いに来たんじゃねぇか、っんのやろぅ」
無骨者はそう唇を歪めながらビールをグイッと呷った。
無骨者の怒りは無理も無かった。
かれこれ僕がこの店に来てたら一時間近くは経っているはずだ。
一時間経っても一向に出て来ない餃子に痺れを切らし、「まだか」と催促すれば、「忘れてた」とそっけなく言われ、挙げ句の果てには「食うのか?」と聞かれたのだ。
おもわず僕はふっと微笑んだ。
さすが破滅店だ、と微笑みながら、餃子を作り始めた連司の背中に「いくら」と呟き、ポケットを弄った。
連司はフライパンの上で油を回しながら、「500円」とぶっきらぼうに言った。
立ち上がって千円札を差し出すと、ふとそこで初めて太宰と目が合った。
太宰は、麺の入っていない五目やきそばを箸でそこらじゅうほじくり回しながらソッと僕を見ていた。それはまるでマユゲを落書きされた野良犬のような淋しい顔だった。
「はい、おつり」
連司が赤いデコラのカウンターの上に、500円玉をペシン!と叩き付けた。
僕はそれをポケットに入れながら、もう一度店内を見渡した。
そこには昭和五十年代のアナーキーな世界が貪よりと広がっていた。
油でネトネトになったサッシ戸を開けた。
当然、連司から「ありがとうございました」という言葉はない。
店を出ると、新宿の生臭い夜風が僕を包み込んだ。
歌舞伎町のホストらしき男が、グデングデンに酔っぱらった風俗嬢らしき女を背中に担いで歩いていた。
男の肩でぐったりと眠る女は、海亀のような顔をしていた。

あれから数年経った。
相変わらずその店はいつも閉まっており、『冷やし中華はじめました』のチラシも貼りっぱなしだ。
新宿の町は日に日に綺麗になっていく。
町を行き交う人々も、ラブ&ピースを絵に描いたような幸せそうな人達ばかりだ。
この町はいつからこんな嘘つきな町になってしまったのだろう。
しかし、一本細い路地を入ると、この町の本当の姿が見える。
薄汚くて油臭くて野蛮でマズくて危険な中華料理店。
そこにラブ&ピースなヤツなんて一人もいない。
そこには人生に正直な破滅者しかいない。
そんな破滅店には、ショーケンの唸り声が良く似合う……






